
《和子は又々こんな記事を見た~》
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
夫を亡くした70代女性が入院中に考えた
“はた迷惑な”行為
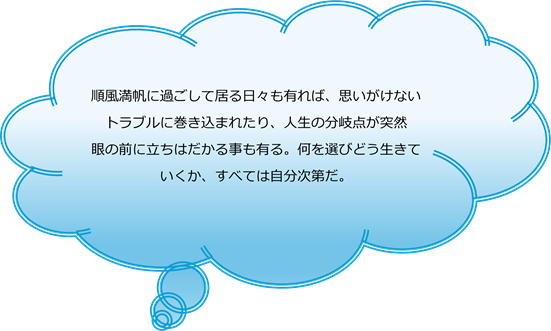
冨美子は毎朝目が覚めるとまず、仏壇に手を合わせる。仏壇には爽やかな
笑顔を見せる夫の写真が置かれている。夫が亡くなったのは1年前。
冨美子が74歳のときだった。78歳という年齢を感じさせない元気さが
あった夫は家で突然倒れ、救急車で搬送。そのまま帰らぬ人と
なってしまった。病名は急性心筋梗塞だった。別れの心構えさえ
できないまま、夫に先立たれ、冨美子は1人暮らしとなってしまった。
2階建ての一軒家は1人で住むには広すぎた。娘の幸代も、結婚し、
家を出て行ってからは会うことが極端に少なくなっていた。
冨美子は仏壇の前から立ち上がり、朝食の準備をする。昔であれば、
あれこれと料理をしていたのだが、1人前の料理を作っているとわびしい
気持ちになるため、最近は電子レンジで温めるだけの簡単な調理のみに
なっている。身近に頼れる人もおらず、最近は足腰が弱くなったことも
あって、この先どうしていけばいいのか不安もあった。
いつ砕けるかも分からない薄氷の上を歩くような孤独な生活のなかで、
冨美子が唯一楽しみにしているのは、疎遠になっていた娘・幸代との電話だった。
夫の葬儀で数年ぶりに顔を合わせてからは、遺品整理などを手伝って
もらったり、わずかな交流が生まれていた。幸代は日中、スーパーで
パートタイムの勤務をしている。夕方ごろに仕事が終わってから家事などを
済ませ、時間が作れるのはだいたい夜の8時以降だった。冨美子は時間が
すぎるのをじっと待って、8時になるや携帯で幸代に電話をかける。
「もしもし、幸代」
「はいはい、どうしたの?」
幸代の返事はいつもおざなりだ。パートや2人の大学生の子供の面倒などで
疲れているのだろう。「元気にしてる? 最近は急に暑くなってきたでしょ?
ちゃんと水分を取らないと危ないわよ」
「大丈夫。昨日もそんなこと言ってたよ」
「そう? でも、心配だから。私もちょっと体調が悪くてね……」
幸代の気を引こうと、冨美子はうそをつく。
「何かあったら、前にあげた緊急通報ボタンを押して。それがあれば、
救急車がすぐに来るから」 冨美子は首に下がっている、赤い文字で“SOS”と
書かれた緊急通報ボタンを見る。夫が亡くなった後、幸代に渡されたものだった。
「今度のお休み、顔くらい見せに来なさいよ。一緒にご飯でも食べましょうよ」
「何回も言ってるでしょ。そんなの無理。忙しいんだから」
携帯電話越しに、幸代が舌打ちをするのがかすかに聞こえた気がした。
「話ってそれだけ?」
「え……?」
「終わりなら、切るけど」
幸代の冷たい言葉に冨美子は胸が締め付けられた。返す言葉は出てこなかった。
「ごめん、ちょっと忙しいから。じゃあまたね」
幸代は電話を切ってしまった。冨美子は無言で携帯を耳から離した。
ひとりぼっちの部屋は広く、暗く、そして寒かった。
緊急通報ボタンを押して救急車を呼んだ

あの日以来、冨美子が電話をかけても幸代が出ないことが多くなった。
毎日のように電話をかけていたから、うっとうしく思われて
しまったのかもしれない。幸代の声が聞けなくなると、冨美子は本当に
ひとりぼっちだった。テレビをつけて、ニュースキャスターやタレントに
話しかけた。彼らはよくしゃべるのに、誰一人として冨美子の声を聞いては
くれなかった。 ある朝目が覚めると、頭が鉛玉のように重たかった。
ゆっくり立ち上がろうとしても身体にうまく力が入らず、視界が
ぐるぐると回った。車酔いのような状態になり、強い吐き気に襲われた。
冨美子は自分がどういう状態なのか理解できなかった。
助けてと叫ぼうとしたが、体が言うことを聞かない。無理やり寝返りを打ち、
冨美子は枕元から何とかつかみ取った緊急通報ボタンを押した。
救急車が到着するまでの10分。しかしその10分は、70年以上もの
人生のなかで経験してきたあらゆる10分よりも長く、そして苦しい
ものだった。自宅にやって来た救急隊員は冨美子を担架に乗せて、
救急車へと運び込む。病院に搬送されながら、冨美子はもうこのまま全てを
手放してしまってもいいのかもしれないと思った。
しかし診断の結果は熱中症で、点滴を打ちながら寝ているうちに気分は
落ち着いてしまった。 「あら、起きられました?」
点滴を交換していた看護師が、冨美子に気づく。
「……今は、何時ですか?」
「今は9時を過ぎたところです。ちょうど3時間くらい寝られて
いたようですね。どうですか、ご気分は?」
視界は広く、声もはっきりと聞こえてくる。頭も重くない。
「はい、大丈夫みたいです」
看護師は冨美子の返事を聞き、ほほ笑んだ。

「良かった。でも緊急通報ボタン、ちゃんと使えて良かったですね」
そこで冨美子は最後の気力を振り絞って緊急通報ボタンを押したことを
思い出す。「ええ。夫を亡くしたときに、娘が私1人になるからって
持たせてくれたんです。いつもはこう、ペンダントみたいに首から下げててね、
寝るときだけは首が絞まると危ないから枕元に置いてたのよ」
「すてきな娘さんですね。とってもお母さん思いじゃないですか」
「いやいや、最近はお邪魔虫扱いですよ。用もないのに電話してくるなって
言われたばっかりでねぇ」
「そんなのきっと本気じゃありませんよ」
看護師との会話がはずみ、冨美子は久しぶりに会話ができることの喜びを
感じていた。起き上がれなかったときはどうなるかと思ったが、
何事もなかった今となってはまさにけがの功名だった。
心配で飛んできた一人娘
さらに冨美子が念のためと勧められた検査を終えて、夕方ごろ病室に
戻ると、ベットの脇には見慣れた姿を見つけることもできた。
「幸代……?」 「お母さん、大丈夫⁉」
勢いよく振り返った幸代が立ち上がる。幸代は冨美子へ駆け寄って手を握り、
何でもないことを理解して息を吐いた。
「病院から電話があって、仕事を早上がりさせてもらって来たのよ」
「ああ、そう言えば、家族の連絡先を聞かれたっけ」
「もうしっかりしてよ。自分で気を付けてって言っておいて、お母さんが
倒れたら意味ないじゃない」 幸代の言葉に冨美子は頰を緩める。
「大げさよ、もう。全然大丈夫だから。一応2日は状況も見るために
入院する必要があるってお医者さまがおっしゃってたけどね。今すぐ
退院したって平気だよ」
「ばか言ってないで、ちゃんと安静にしてて。私、家に帰って着替えを
取ってくるから。休みももらったし、入院中は実家に泊まるね」
「まぁ……」
冨美子はうれしくて言葉が出なかった。ぼうぜんと立ち尽くす冨美子を見て、
幸代があきれたように笑う。
「当たり前でしょ。仕事なんてやってる場合じゃないもん」
幸代がここまで自分を心配してくれるなんて。感激で胸がいっぱいになる。
「ほんと、お父さんのこと思い出して、血の気が引いたわ」
「心配をかけてごめんなさいね」
口にした言葉とは裏腹に、内心は喜びで満ちあふれていた。
2日間の入院期間中、幸代はほとんどの時間を病室で過ごしてくれた。
看護師たちも冨美子を目にかけ、優しい言葉をかけた。それは冨美子にとって
何にも代えがたい幸せな時間だった。
しかし夢が必ず覚めるように、幸せだった時間は終わってしまう。
看護師に見送られて退院すると、幸代は当たり前のように自分の家に
帰ってしまった。うなだれて伏せた視線の先、冨美子の胸に下げられた
ペンダント型緊急通報ボタンが目に入る。その瞬間、冨美子の脳裏に
ある考えが浮かんだ……。
🧿 つかの間の娘とのふれ合いをかみしめた冨美子の「ある考え」とは……?
♾️♾️♾️ つづき ♾️♾️♾️
♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️